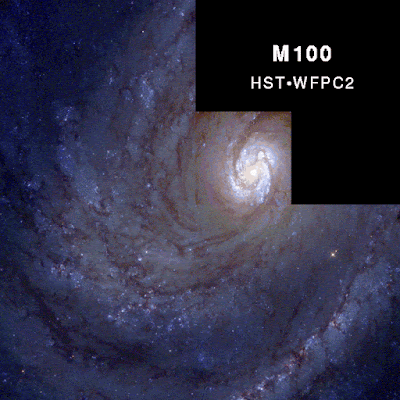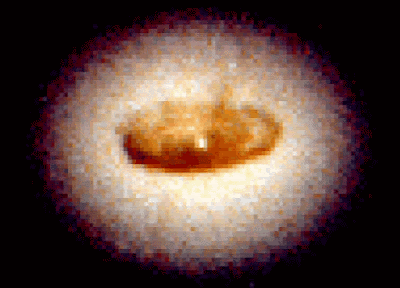渦巻き銀河M90は、我々の天の川銀河に最も近い銀河団であるおとめ座銀河団の中心付近にあります。NGC4569とも呼ばれるこの銀河は、非常にコンパクトで明るい中心核を持っています。おとめ座銀河団に近接しているため、M90は青方偏移を示し、遠ざかるというよりむしろこちらに向かってきていることがわかります。ほとんどの銀河は赤方偏移を示し、私たちから遠ざかっていくことを示しています。赤方偏移と距離の関係を正確に測定することは、宇宙のスケールを示すことになり、最近盛んに議論されているテーマです。
(翻訳:2023/2/3)
関連記事
局部銀河群に属する NGC205銀河
子持ち銀河 M51
乙女座銀河団
<<トップページへ>>