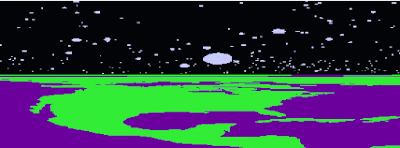ブラックホール越しに景色を眺めるとどのように見えるのでしょうか?今日はその疑問に答えてくれる画像を紹介します。上の2枚の画像は、重力の理論に基づいてコンピュータで作成されたシミュレーション画像です。左側の画像はオリオン座近辺の星空の様子を示しています。画像の中央からやや右寄りに、オリオンの三つ星が並んでいるの分かると思います。右側の画像も同じ星空を表していますが、違うのは星空の手前にブラックホールが配置されていることです。ブラックホールの周りではその強い重力の影響で光の軌道が歪められます。このことから、背景となる星空も左の画像に比べて大きく歪んでいます。右の画像には奇妙な点がいくつも見られます。まず、左の画像に見えていた星の多くが、右の画像では2つの星に分裂しています。分裂した星はブラックホールを挟んで両側に見えています。これはブラックホールの強い重力によって星の光が二手に別れてしまうために起こる現象です。また、この画像では分かりにくいですが、理論的にはブラックホールの直近では、実は全天のすべての星が見えています。あらゆる方向からきた光がブラックホールの重力に絡め取られ、ブラックホールの周りを光が軌道運動することからこのような現象が起こります。ブラックホールは物質の密度が高くなった極限の状態であると考えられています。現時点ではまだブラックホールの直接の検出は行われていませんが、連星系、球状星団の中心領域、銀河の中心領域などからブラックホールの存在を示唆する間接的な証拠が多数見つかっています。
(執筆:2017/11/30)
関連記事